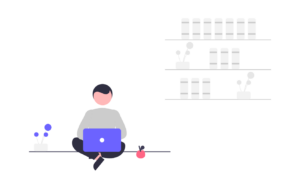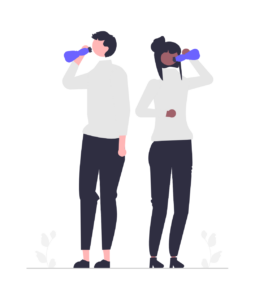ストレスが健康に与える影響とは?セルフケア方法もご紹介

「仕事もプライベートも充実しているのに、毎日がつまらない」「頻繁にイライラしたり落ち込んだりする」という人は、気がつかないうちにストレス症状が出ているのかもしれません。
ストレスは目に見えないため自分では気づくことが難しく、放置してしまうと心身にさまざまな悪影響が出てきます。
今回はストレスが健康に与える影響やストレスのサインに気付くためのポイント、セルフケアの方法をご紹介します。
社会人が日頃から感じやすいストレスの種類

現代社会には多くのストレスがあります。
まずは「どのようなストレスがあるのか」を知り、身近なストレスの原因を確認してみましょう。
<仕事でのストレス>
- 仕事の量が多い
- 仕事の質(難易度が高い/低い 等 )への不満
- セクハラ・パワハラなど、対人関係の問題がある
- 将来への不安がある
など
<プライベートでのストレス>
- 友人・近隣住民・家族などの人間関係の問題がある
- 将来のお金に関する不安がある
- 健康面の不安がある
など
これらのストレスは、放置すると悪化する傾向が高いとされています。また、なかには複数の項目が当てはまる人もいるかもしれません。ストレスを感じたら、溜め込まずに周りに相談することが大切です。
ストレスが身体的な健康に与える影響とは?

ストレスが健康に与える影響はさまざまです。最初は心や身体に小さな異変が現れ、放置すると病気になる可能性があります。
日頃からストレスを感じやすい人は、些細な心や身体の変化にも注意しておくことが大切です。
ストレスで起こる心や身体の異変
ストレス値が処理能力(キャパシティー)を上回ると、心や身体にさまざまな異変が起こることがあります。例えば、慢性的な怠さ、気持ちの浮き沈みなどです。
職場環境、仕事の種類、私生活での満足度など、何によって強く影響を受けるかは人それぞれです。
ストレスによる異変が顕著に現れる部分は、大きく分けて以下の3つです。
| 項目 | 概要 |
| 心 | ・悲しくて憂うつな気分になる不安 ・緊張でイライラする ・無気力でやる気が出ない |
| 体 | ・食欲がなくて痩せた ・寝付きが悪くて朝早く目が覚める ・動悸で血圧が高くて手や足の裏に汗をかく |
| 行動 | ・消極的な気分で、周囲との交流を避けている ・飲酒と喫煙の量が増えた ・身だしなみが整っておらず落ち着きがない |
このように、ストレスは心や身体に悪い影響を与える可能性があります。ストレスによる慢性的な不調を防ぐためにも、自分の心と体の状態をよく観察し、対処することが重要です。
厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルスをサポートする”こころの耳”」では詳しいストレスサインの種類が説明されています。もっと詳しく知りたい人は以下もご確認ください。
参考:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳「3 ストレスへの気づき」
ストレスが原因でなる病気
心身の異変を放置して症状が悪化した結果、病気になってしまう可能性もあります。
その人の性格・置かれている環境・ストレスの種類などによって影響はそれぞれです。まずは「ストレスが原因」で発症する可能性のある病気を確認してみましょう。
| 病気の部位 | 病気の種類 |
| 呼吸器 | ・気管支喘息 |
| 循環器 | ・本態性高血圧症 ・狭心症 ・心筋梗塞 |
| 消化器 | ・胃潰瘍・十二指腸潰瘍 ・過敏性腸症候群 ・潰瘍性大腸炎 ・心因性嘔吐 |
| 内分泌・代謝系 | ・単純性肥満症 ・糖尿病 |
| 神経・筋肉系 | ・筋収縮性頭痛(緊張型頭痛) |
| 皮膚 | ・慢性じんま疹 ・アトピー性皮膚炎 ・円形脱毛症 |
| 整形外科領域 | ・慢性関節リウマチ ・腰痛症 |
| 泌尿器 | ・夜尿症 |
| 目 | ・眼精疲労 |
| 耳 | ・メニエール病 |
| 口腔 | ・顎関節症 |
※必ずしもストレスが原因で発症するとは限りません
こうしたデータからも、ストレスは心を苦しめるだけでなく、身体にも大きな悪影響が現れることが分かります。
ストレスで心身に悪影響を感じている人は、早めに病院の受診やカウンセリングの利用などをご検討ください。
ストレスのサインを見落とさないためには?

ストレスのサインを見落とさないために、日常生活ではどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ポイントを3つご紹介します。
ストレスが溜まりやすい状況について知る
ストレスが溜まりやすい状況を把握するには、以下の方法があります。
- 日々の行動を日記に書いたり記録したりする
- 心身のサイン・異変を観察する
- 身近な信頼できる人に相談する
- カウンセリングを受ける
- ストレスチェックを活用する
など
ストレスが溜まりやすい状況は人によって異なります。自身のストレスが溜まりやすい状況を知るには、その日の気分や行動を振り返り、ストレスの引き金を把握しましょう。日記や記録をつけると、どんな状況でストレスを感じるのかが分かりやすくなります。
身体の不調や気分の変化は、心の疲れを知らせる重要なサインです。ストレス診断ツールや職場のストレスチェックを活用し、客観的にストレスレベルを評価できる効果的な対策も考えてみてください。
ストレスサインを見逃さないためにも、例えば、軽い運動やリラクゼーション、趣味の時間を取り入れるなど、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。
まずはストレスが溜まりやすい状況を把握し、ストレスと向き合いながら心身の健康のバランスを維持していきましょう。
ストレスチェックを受ける
2015年12月より「常時50名以上の従業員が働く企業」に、労働安全衛生法に基づくストレスチェックが義務付けられています。そうした企業で働いている場合は、自社で利用できるストレスチェックも活用して、ストレスのサインが出ていないかを確認してみましょう。
ストレスチェックにより「高ストレス」と判定された場合は、医師との面談を受けることができます。また医師との面談後に、以下の調整が行われることで、心身の不調・悪化を未然に防ぐことができる可能性もあります。
- 就業場所の変更
- 作業の転換
- 労働時間を短くする
- 残業を減らす
など
また、皆さんのストレスチェック結果は、職場環境の改善にも役立てられています。
ストレスチェックの全体結果から、負担の大きな組織・職種・その背景にある原因をデータで確認できるため、会社が職場改善を行う際の参考になります。
結果的には「職員1人ひとりにとっての働きやすい職場環境」が実現されるメリットも考えられます。
参考1:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(4P
参考2:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」
参考:3:厚生労働省「場環境改善ツール|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
カウンセリングを受ける
メンタル不調の予防にはカウンセリングの利用が効果的です。自分自身でストレスのサインに気付くのは難しいため、心理学の専門知識を持つカウンセラーに相談してみることがお勧めです。
アドバンテッジ相談センターでは、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー、精神保健福祉士のいずれか、または複数の資格を持つカウンセラーが話をお聴きします。
カウンセラーと話すなかで自分の心や体の状態に目が向き、今まで自覚していなかったストレスの存在に気づけることもあります。また、認知行動療法でストレスが蓄積している原因を論理的に探っていくため、ストレスに対処する力が高まっていくことも期待できます。
安定感のあるしなやかな心を作りたい人は、ぜひアドバンテッジカウンセリングをご利用ください。
カウンセリングのご予約はこちら:https://user.counseling-platform.com/login?vid=1
ストレスに負けないセルフケア(コーピング)の方法

最後にストレスを減らすセルフケアの方法をご紹介します。
基本的なコーピングの方法は
- 情動焦点型
- 認知的再評価型
- 問題焦点型
の3つです。
まずはこの3つの方法を実践して、心身をリフレッシュさせてみましょう。
情動焦点型
情動焦点型のコーピングとは、ストレスに対する考え方・捉え方を変える方法です。ネガティブ思考な人は、相談をすると気分を整理したり発散したりできるので、自分1人では思い浮かばなかった思考に気づける可能性があります。
特徴は以下のとおりです。
- 感情を落ち着かせることが目的
- 問題の解決が困難な状況で効果的
- 自分の感情を自分で認める方法
- 周囲や外部に気持ちを受け止めてもらう方法
具体例としては、友だちに相談して感情を共有することで気持ちをリラックスさせたり、日記に気持ちを書き出したり、心を整理させる方法になります。
問題そのものの解決だけではなく、自分の感情・気持ちを落ち着かせる「ストレスの軽減」が目的です。
特に、問題の解決が難しいシーンに直面したときに活用してみましょう。
認知的再評価型
ストレスの原因に対してポジティブシンキングで対応する方法です。ノルマや目標などのプレッシャーに対して「期待されている」とポジティブに捉え直すことで、ストレスの緩和が期待できます。
特徴は以下の内容です。
- ストレスに対してポジティブに向き合うことが目的
- 自己成長のきっかけにつながる
- ストレッサーに対する認知の仕方(考え方)を変化させる方法
具体例としては、上司から与えられた課題に「期待されているから難しい目標が与えられたんだ」と思うことが挙げられます。実際に「あなたならできる」と思われているからこそ、難しい課題や問題を任されることもあります。相手の期待する気持ちを原動力にして、前向きに挑戦してみても良いかもしれません。
問題焦点型
問題そのものを変化させたり取り除いたりしてストレスの原因をなくす方法です。問題と向き合う「接近型コーピング」と、問題との直面化を避ける「回避型コーピング」があり、バランス良く使い分けることが大切です。
特徴は以下のとおりです。
- 「接近型コーピング」は、ストレッサーに対し改善アクションを行うもの
- 「回避型コーピング」は、そもそも問題解決を目的にしなかったり、問題から意識を逸らしたりすることで気持ちを落ち着けるもの
- 接近型コーピングを試し、うまくいかなければ回避型コーピングを選択することがおすすめ
具体例として、苦手な人がいる際に「コミュニケーションを取って関係を良くしようと努力すること」が接近型コーピング。
「コミュニケーションを避けて関係を断とうとすること」が回避型コーピングです。
人間関係がストレッサーの場合には「接近型コーピング」が根本的な解決になることもありますが、うまくいかないこともあります。問題ごとに、両方のコーピング方法を組み合わせて、ストレスと上手に付き合っていくことが大切です。
参考:ストレスコーピングとは。意味や種類、今すぐできる実践方法を解説 | アドバンテッジJOURNAL
自分1人でできることは対処し、難しいと感じた部分は周囲の人のサポートを受けることも重要です。1人で解決しようと思わずに、まずは周囲の人や専門家に相談してみましょう。
参考:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳「4 ストレスへの対処」
参考:知ることから始めよう こころの情報サイト 精神保健研究所70周年記念事業「ストレスとセルフケア」
まとめ:心身の健康を維持するためにはストレスチェックが大切

日頃から感じるストレスが大きくなって心身のストレス処理能力を上回ると、心や身体にさまざまな異変・病気が現れることがあります。
自覚がないままストレスを溜め込んでしまうこともあるため、心身の変化や日常の出来事を振り返り、1日のなかで数分だけでも「自分に意識を向けてあげる」ことが大切です。
ご紹介したセルフケアの方法やカウンセリングを活用することで、自分に合ったストレス軽減方法を探してみましょう。