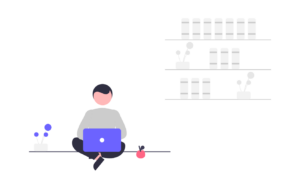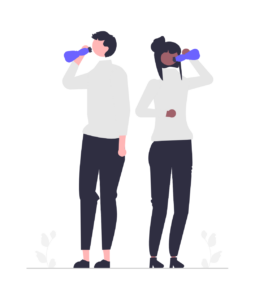新米ママ・パパ必見!子育て中の親なら知っておきたい「ソーシャル・ウェルビーイング」とは?
子どもが未就学児の時期、親として子どもへの接し方や発達について悩むことは決して珍しいことではありません。「この対応で良いのだろうか」「どうして言うことを聞いてくれないのだろう」と戸惑う瞬間もあるでしょう。
この記事では、ソーシャル・ウェルビーイングに関するテーマとして、子どもの発達や心理を理解し、子育て中の不安を軽くするヒントをお伝えします。
自分だけじゃない!子どもとの向き合い方に悩む親は多い

子育てをする中で、親が子どもの行動や反応に悩むのは自然なことです。特に未就学児の時期は、言葉や感情が発達途中のため、親子間ですれ違いが生じやすい時期です。
<よくある悩みの例>
- 急に泣き出したり、癇癪を起こしたりすることが多い。
- 親の言うことに反発ばかりしてくる。
- 他の子どもと比べて発達が遅れているのではないかと心配。
子育てや子どもに関する悩みは子どもと2人きりの時や、家庭内でのふとした瞬間に生まれるものが多く、1人で思い悩むうちに「うちの子だけがこうなんじゃないか…」と不安になることもあるかと思います。個性や成長速度は子どもによって異なりますので、必要以上に他の家庭と比べたりせず「自分たちの個性やペースを意識しながら成長していくことが大切」と考えることから始めましょう。
アドバンテッジJOURNALでは、子育てに役立つ記事も掲載しています。
EQ(感情の知能指数)を意識しながらの子育て方法などの情報を掲載しているため、詳しく確認したい人はぜひご確認ください。
子育てにも役立つ! コミュニケーションの根源的能力“EQ”活用のヒントと、広がる可能性 | アドバンテッジJOURNAL
子育て中の親なら知っておきたい、ソーシャル・ウェルビーイングとは?

今回ご紹介するソーシャル・ウェルビーイングとは「深い信頼・愛情による人間関係や、社会的なつながり」を意味する言葉です。家族や地域社会と繋がることは、親子の成長や安心できる家庭づくりに大きな影響を与えます。
①親自身の健康が子どもの安心につながる
親が心身共に健康な状態であることは、子どもの健全な発達に欠かせない要素です。親が不安を感じていると、子どもも同じように不安を抱え、落ち着かなかったり、イライラしやすくなったりといった悪影響が出ることがあります。一方で、親がリラックスし、穏やかな気持ちでいることができれば、子どもも安心してのびのびと過ごせます。
②子どものロールモデルになる
ソーシャル・ウェルビーイングが充実している場合、親だけでなく、親戚や地域の人たちなど、さまざまな大人と関わる機会が生まれます。子どもにとって親以外の大人とのふれあいは、将来の人生におけるロールモデルを学ぶ機会や多様な価値観を知るきっかけになるでしょう。
また、ソーシャル・ウェルビーイングを意識した親の姿勢は、子どもに「周りの人と関わること」の大切さを伝えることができます。子どもが自発的にコミュニケーションの取り方や、助け合う行動などを学ぶことにも繋がります。
③子育て中の孤立を防ぐ
家族だけで子育てをしていると、社会から孤立しているように感じられることがあります。周囲のサポートが得られる状態や、子育てコミュニティなどに所属し、ソーシャル・ウェルビーイングを実現することで、安心した気持ちで育児に向き合うことができるようになります。
特に共働きの家庭は、子どもが一人で過ごす時間も多々あります。その際、子どもにとって「親や家族以外に頼れる場」があることは、子どもの心の安定につながります。親にとっても、安心して子育て以外の時間を過ごすことができるでしょう。
このようにソーシャル・ウェルビーイングは、親と子どもの両方にとって幸せな未来を築くための重要な視点です。
子育て期に実践したいソーシャル・ウェルビーイングを高める方法

それでは、上記のようなソーシャル・ウェルビーイングの視点を重視した子育てを行うにはどうしたらよいのでしょうか。いくつかの具体的なアクションをご紹介しますので、家庭の状況や子育て方針に合わせて参考にしてみてください。
①子どもの好奇心を大切にする
0歳~6歳の頃というのは、だんだんと自己主張が強くなり、さまざまな興味関心が生まれる時期です。子どもの「やりたい!」という希望に応え、好きなことや新しいものに触れる機会を作りましょう。
大人はSNSでのコミュニケーションや趣味の活動を通じて、ソーシャル・ウェルビーイングを充実させることができますが、子どもはそうした手段を持ちません。子どもの将来のためにも「外の世界とのつながり」を親が与えてあげることが重要です。
例えば、子どもが興味を持った習い事に参加したり、地域の子ども同士で遊べる場に参加するなどが挙げられます。また、子どもが「自分でやりたい!」といったことに挑戦させてあげることも大切です。つい親がやってあげたくなりますが、子どもの挑戦心を優先し、親は見守ることも重要です。
②子どもによりそった声かけをする
親子の絆を深め、子どものコミュニケーション力を育むためにも、親が子どもによりそった声かけをすることが大切です。
例えば「怒っちゃったんだね」「悲しかったんだね」と子どもの今の感情を言葉にしてあげると、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じ、気持ちが落ち着きやすくなります。また、「赤い靴と青い靴、どっちを履きたい?」と子どもが自分で決められる場面を増やすことで、自主性が育ちます。
さらに子どもが大きくなってくると「どうして?なぜ?」と聞かれることが増えてきますよね。そんな時、すぐに答えを教えるのもいいですが、「どうしてだと思う?一緒に考えてみようか」と問いかけると、子どもが考え・行動することができるようになります。
③地域や自治体などのサポートを活用する
子育てにはさまざまな悩みがつきものです。子育ての悩みは1人で抱え込まず、地域や自治体などのサポートを活用してみてください。子どもにとっても、ほかの子どもや大人と交流をする場となり、子どもの成長のきっかけにもつながります。
<例>
- 子育て支援センター
- 保育園、幼稚園
- 地域の子育てコミュニティ
など
ただし環境の変化や影響に敏感な子どももいるため、気づかないうちにストレスを溜めてしまうことがあります。親子にとって安心できる場を探すことが大切です。
④専門家のカウンセリングを活用する
子どもの発達や対応について、専門的なアドバイスを受けたい場合には、カウンセリングを活用することもおすすめです。カウンセリングでは子どもの行動や心理に関する専門的な知見をもとに、皆さまのソーシャルウェルビーイングの実現をサポートしています。子どもとの関わり方に悩みがある人は、ぜひ当社のアドバンテッジカウンセリングをご活用ください。
また、子育て中の不安や悩みをカウンセリングの場で吐き出すだけでも、心が軽くなるなどのポジティブな効果が期待できます。当社のカウンセリングではカウンセラーのプロフィールを事前に閲覧することができ、話を聞いてほしいカウンセラーをお選びいただけます。カウンセリング方法もメールやオンライン面談、SNSを使ったチャット相談など、さまざまな方法をご用意しておりますので、子育て中でお忙しい方にもおすすめです。
カウンセリングのご予約はこちら:https://user.counseling-platform.com/login?vid=1
まとめ:ソーシャルウェルビーイングを意識して周囲のサポートも受けながら子育てを楽しんでみましょう

子どもは、親や身近な家族、友達、地域の人たちなどのさまざまな人間関係の中で育ちます。親子がそれぞれのソーシャル・ウェルビーイングを充実させることで、親子がともに健やかな成長を実現することができます。
子育ての不安や悩みを1人で抱えずに、ぜひ地域のサポートや専門家の力を活用しながら、子どもを見守り育てていきましょう。