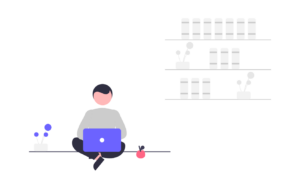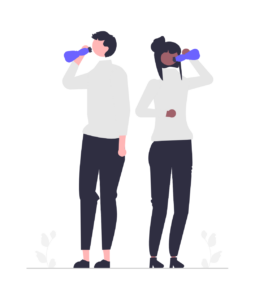組織改革とは?進め方から事例まで詳しく解説
2019年に開始された働き方改革の推進により自社でも働く環境の見直しを進めてきたけれど、人材を確保するためには組織改革により会社が大方針を掲げることが必要だと感じている人はいませんか?
この記事では組織改革について詳しく解説します。
組織改革とは?

組織改革とは、企業や団体が継続的に成果を挙げることを目指して組織の仕組みを改善する取り組みを指します。
企業や団体がスムーズに成長をする上で、目的に応じて組織の構造や人員配置、業務の進め方などを見直す必要があるため、組織改革が行われます。
また従業員の立場から組織改革を見てみると、組織の構造・制度・文化・業務プロセス・人員配置などの環境が大きく変化するため、負荷が大きい取り組みと言えるでしょう。
組織改革の意味を深く理解する上で、混同されやすい言葉を2つご紹介します。
組織変革と組織改革の違い
組織改革と混同されやすい言葉の1つに「組織変革」があります。
組織変革とは企業や団体が継続的に成果を挙げるのを目的として、組織全体の価値観、行動様式、戦略、採用のあり方などを根本的に変えることです。
組織改革と組織変革の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 組織改革 | 組織変革 |
| 変化する内容 | ・やり方(小さな部分)を変える | ・あり方(大きな部分)を変える |
| 変化の対象 | ・組織構造 ・ルール ・制度 | ・組織文化 ・価値観 |
| 期間 | ・半年〜数年 | ・数年〜 |
| よく使われる場面 | ・企業や団体の構造見直し ・業務の進め方の見直し ・人員などの見直し | ・ビジョンの更新 ・組織文化の改革など・抜本的な変化 |
「組織改革は現状の延長線上で変化が進む」一方で、「組織変革では今の枠組み自体を壊して一新に近い状態に変化させる」点が大きな違いだと言えるでしょう。
組織改革と働き方改革の違い
組織変革と同様「働き方改革」も組織改革と混同されやすい言葉です。
働き方改革とは、厚生労働省の働き方改革特設サイトで「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できる改革」と定義づけられています。
組織改革と働き方改革の主な違いは次の通りです。
| 項目 | 組織改革 | 働き方改革 |
| 目指すもの | ・組織全体の最適化 ・競争力の強化 ・業績向上 | ・生産性の向上 ・労働時間の適正化 ・ワークライフバランスの実現 |
| 変化の対象 | ・組織構造・ルール ・制度 | ・労働時間 ・勤務場所 ・制度(テレワーク、副業、時差出勤など) |
| 期間 | ・半年〜数年 | ・数ヶ月〜1年 |
| よく使われる場面 | ・企業や団体の構造見直し ・業務の進め方の見直し ・人員などの見直し | ・人手不足への対応 ・離職率の改善対策 ・従業員エンゲージメントの向上対策 |
どちらの改革も従業員は新しい環境への適応を余儀なくされるため、企業はそのサポート体制を構築しておくのが大切です。
組織改革に必要なこと

組織改革をスムーズに進めるために必要なことは以下の通りです。
- 経営層の強いリーダーシップと覚悟
- 現場のリアルな声を吸い上げる仕組みの構築
- 目的とビジョンの言語化
- 社内コミュニケーションの再設計
- 変化に不安を感じる従業員へのサポート
- 心理的安全性の確保
- 組織の「感情の流れ」に敏感になる
- AIやツールの導入だけで終わらせない
心理的安全性とは、組織内で自分の意思や感情を自由に表現でき、拒まれたり罰せられたりしないと確信できる状態を指します。組織改革が進むと、一時的に従業員の環境が大きく変化するため、心理的安全性が揺らいでしまう可能性があります。
そして心理的安全性が確保されない状態の長続き、新たなルール・体制への適応負荷が増す、先行きの見えない組織改革による不安感が強まるなどの状態が続くと、従業員がメンタル不調に陥る可能性も生じるでしょう。
組織改革が進んでも、肝心の社員が不調になってしまっては、元も子もありません。
このような時こそ、カウンセリングが大きな役割を果たします。
組織改革により大きく変わった会社の環境に順応できず、ストレスが溜まった社員の不満・不安・悩みの解消にカウンセリングをお役立ていただけます。
利用者満足度97%のアドバンテッジカウンセリングでは働き方に応じた柔軟な相談方法を提供しているため、組織改革に伴う不安やストレスにも、すぐに寄り添える環境が整っています。
興味のある方は次のページもご覧ください。
メンタル不調者ゼロ + 社員のパフォーマンス向上を目指すなら | アドバンテッジ カウンセリング
企業における組織改革の成功事例

企業における組織改革の成功事例を3つご紹介します。
トップダウンとボトムアップの両輪で組織改革を推進した事例
ある酒造メーカーは、長らくビール市場でトップのシェアを誇っていました。しかし消費者のニーズの多様化、競合他社の商品の大ヒットなど、複数の要因からシェアトップから陥落してしまいました。
その出来事をきっかけに組織改革に取り組みはじめたものの、他責思考や慢心しやすい組織風土がなかなか変化せず、うまく改革を進められずにいた状況です。
危機感を抱いた当時の社長は、若手社員や労働組合を含めた座談会、社内経営塾の講演会などを開催し「自分たちの組織はどうあるべきか」のメッセージを強く発信し続けたのです。
この結果、従業員が全員でブランドを育成していくという新しい組織風土が生まれ、組織改革を成功させることができました。
トップダウンとボトムアップの両輪で組織改革を推進し、成功に導いた好事例だと言えるでしょう。
組織改革で課題の「見える化」をし従業員が主体的に行動し始めた事例
ある食品メーカーでは長期にわたる成功体験に依存し、新しいことに取り組むのに消極的な組織風土が芽生えつつありました。
しかしコロナ禍により、インバウンド需要の低下や原料の輸入先の状況を先読みできない外的な課題が発生しました。同時に、テレワークの影響で従業員の状況や仕事の進捗が把握できないという、内的な課題も顕在化してきたのです。
経営陣はこの状況に危機感を持ち、強い指揮命令による管理を強化したものの、かえって従業員は自律的な行動をしなくなってしまいました。
そこで経営陣は「社員・組織の現状を認識」し、課題の見える化や改革に向けた意識向上をしてもらうため勉強会を開催しました。
勉強会をしたことで社員が主体的になって組織改革は活発化し、経営陣から従業員への権限移譲もスムーズに進みました。会社全体が「自主的に成長できる組織」へと変化したのです。
最初に組織の持つ課題を見える化し、経営陣と社員が問題を共有できたため、全員で解決に向けて組織改革に向き合えた好事例だと言えるでしょう。
小さな成功体験を積み上げ社内に改革の文化を根づかせた事例
ある美容機器メーカーではヒット商品を生み出すことができ業績を安定させていました。しかし次第に従業員の成長意欲は低下し、若手の従業員から見て理想となるロールモデルが不足する事態となりました。
その結果、3年目~5年目までの若手社員は危機感を持ち、80%が退職してしまったのです。
この状況を改善するため、会社では研修制度を以下のように強化しました。
| 項目 | 概要 |
| ブラザーシスター制度の導入 | ・先輩社員と一緒に成長するのを目的として導入 ・先輩社員を指導役として組織に定着させる ・人事部が月に1回面談し後方支援をする |
| 他社との合同研修の実施 | ・2年目フォロー研修 ・若手社員フォロー研修 |
ブラザーシスター制度では、新入社員と若手社員の離職率を5%までに低下させることに成功しました。
一方合同研修では従業員エンゲージメントが向上し、より前向きな企業文化が生まれることにつながったのです。
研修制度の改革は会社全体から見ると小さな成功体験だったかもしれません。しかしそれが従業員のエンゲージメントを大きく高め、組織改革につながった好事例だと言えるでしょう。
組織改革を失敗させないために心がけたいこと

組織改革を失敗させないためには、前の項目でもご紹介した通り、以下の項目が必要です。
- 変化に不安を感じる社員へのサポート
- 心理的安全性の確保
- 組織の感情の流れに敏感になる
など
このように、従業員のメンタル面への配慮は、組織改革を円滑に進めるうえで欠かせない要素と言えるでしょう。
その取り組みの一環として、新しい環境への適応を支援するカウンセリングサービスの導入も、選択肢のひとつです。
組織改革を進める中では、従業員に大きなストレスがかかります。従業員自身も会社が前向きに改革を進める中、後ろ向きな感情を表現しにくい環境にあることを理解し、サポートすることが大切です。
また当社カウンセリングサービスでは「認知行動療法」という手法がよく用いられますが、この手法では従業員自身に気づきを促すだけではなく、従業員の環境適応を支援し、組織改革を実現をサポートします。
組織改革においてカウンセリングサービスの利用を検討したい方は、次のページもご覧ください。
メンタル不調者ゼロ + 社員のパフォーマンス向上を目指すなら | アドバンテッジ カウンセリング
まとめ

組織改革とは、企業や団体が継続的に成果を挙げることを目指して組織の仕組みを改善する取り組みを指します。
職場環境や働き方が大きく変化する可能性がある組織改革では、社員をサポートするメンタルケアや相談先としてカウンセリング体制を整えておくと良いでしょう。
この記事も参考にして、従業員の感情に配慮しながら積極的に組織改革を進めてみてください。