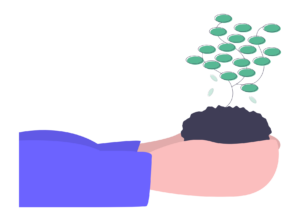健康増進はカンタンにできる?今日から取り組める方法と安心サポートの秘訣

年齢が上がるにつれて「体力の低下や健康状態が気になってきた・・・」という人は多いと思います。特に運動不足はさまざまな健康リスクにつながるため、自分の身体の状態を把握して日々の健康増進に取り組むことが大切です。
今回は「運動習慣を身につけたい」と考えている人に知ってほしい、フィジカル面での健康増進に役立つ情報をお伝えします。
フィジカルウェルビーイングとは

フィジカルウェルビーイングとは、心と身体がエネルギーに満ちた状態です。
近年よく耳にするウェルビーイングとは「身体・精神・社会などのあらゆる面で健康な状態」を表す広義の意味での概念です。病気やケガの有無にかかわらず、心身ともに社会的にも幸せで満たされた状態を指します。
ウェルビーイングは、以下の5つの要素を満たすことで実現できます。
| 名称 | 概要 |
| Career Wellbeing(キャリア ウェルビーイング) | 仕事に限らず、自身が選択したキャリアや人生に満足している状態。 |
| Social Wellbeing(ソーシャル ウェルビーイング) | 家族や友人など、人間関係で深い信頼と愛情を築けている状態。 |
| Financial Wellbeing(フィナンシャル ウェルビーイング) | 資産管理や運用ができており、お金に関する不安がない状態。 |
| Physical Wellbeing(フィジカル ウェルビーイング) | 心身が健康で思い通りに行動でき、ポジティブに活動できている状態。 |
| Community Wellbeing(コミュニティ ウェルビーイング) | 会社や学校、地域社会などに所属し、繋がりあうことに幸福を感じられる状態。 |
ウェルビーイングを構成する5つの要素は、どれか1つでも欠けていると健康のバランスが崩れてウェルビーイングが保てなくなる可能性があります。例えば「身体は健康でも心が疲れている人」は、ウェルビーイングが高い状態とは言えません。
このように、フィジカル面でのウェルビーイングは単に「病気にならない」ことだけでなく、身体的・精神的・社会的な豊かさを実現する土台となります。充実した人生には欠かせない項目なので、ぜひ以下の内容も「自分の心と身体と対話」しながら読んでみてください。
参考:ウェルビーイングの意味。注目される理由や実践事例などを紹介 アドバンテッジJOURNAL
フィジカル面で健康増進を目指すためのポイント

フィジカル面での健康増進には、定期的な運動が大切です。
まずは、自分の身体の状態を知るところから始めましょう。
食事管理・睡眠方法を整えたうえで運動を続けると、長期的な健康増進が実現できます。
健康状態を把握する
会社員の人は定期的に健康診断を受けているかと思いますが、気になる数値や悪い結果をそのままにしていませんか?気になる数値がある人は、改善のためのアクションを始めましょう。
健康増進のためにも、まずは血圧・体重・BMIなどの数値の変化を記録することが大切です。
最近では、ゲーム感覚で楽しく健康状態をチェックできるアプリも多く登場しています。
ウェアラブルデバイスなどの導入することで、日々の運動量や睡眠パターンを管理できるようになりました。運動習慣を維持するモチベーションにもなるため、身近なアプリやデバイスを活用してみてください。
食事・栄養管理を意識する
フィジカル面でのウェルビーイングには、健康的な食事習慣や栄養管理の視点も欠かせません。普段どのような食事を摂っているか、自分の食生活を振り返ってみましょう。
<食事習慣のポイント>
①過不足を避けて適量の食事を摂る
②食事のタイミングを整える
③水分補給を充分に行う
過食・小食はどちらも健康を損なう原因になります。厚生労働省の「食事バランスガイド」を参考に、自分の身体に合わせた食事量を確認してみましょう。
「一気にたくさんの食事を摂る」「朝食を食べたり食べなかったりする」など、不規則な食事習慣にも注意が必要です。
参照:厚生労働省:「食事バランスガイド」について|厚生労働省
質のよい睡眠をとる
近年の研究では、睡眠も身体の健康に大きく影響していることが分かっています。睡眠不足は風邪や病気、事故などの原因にもなるため、質の良い睡眠の確保が大切です。
まずは充分な睡眠がとれているか、日頃の睡眠時間を記録してみましょう。理想の睡眠時間には個人差がありますが、おおよそ毎日7時間~8時間ほどです。日頃から十分に睡眠時間を確保できていない人は、夜更かしや睡眠前のスマホ時間などの「眠る前の睡眠を妨げる行為」がないかを確認してみてください。
<睡眠の質を上げるための環境の見直し>
- 就寝直前のパソコンやスマホの使用を控える
- 日中適度に日の光を浴びる、運動する
- 寝具の質を高める
- 室内の温度や湿度を快適に保つ
必要な睡眠時間には個人差があるので、自分自身が満足できる睡眠習慣を見つけてみてください。
参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター:睡眠と健康の関係について
アドバンテッジJOURNALでは、睡眠トラブルを抱えている人に向けた記事もご用意しております。ぜひ参考にしてください。
参考:仕事のストレスで眠れないときは?睡眠トラブルの原因と対処法を徹底解説 | アドバンテッジJOURNAL
健康な心身を支える運動習慣の身につけ方

バランスの良い食事習慣、質の良い睡眠習慣が確保できたら、次は運動習慣を身につけてましょう。
今回は「社会人になってから初めて運動に取り組む人」や「久しぶりに運動する人」などに向けた、無理なく運動を始められる方法をお教えします。
無理なく続けられる運動をする
フィジカル面でのウェルビーイングを目指すためには、毎日少しでもいいので「続けられる運動」に取り組むことが大切です。
以下の例を参考に、自分の好きなものや気軽に始められそうなものからトライしてみてください。
<無理なく続けられる運動>
- 1日30分ほどの「ウォーキング」
- 仕事・家事の合間の「ストレッチ」
- 1日5分〜10分ほどの「軽い筋トレ」
まずは小さな運動から取り入れてみて、自分の身体の変化を感じてみましょう。
日常生活に運動を取り入れる
意識的に「運動する時間」を設けるのもよいですが、日常生活のなかに運動を取り入れる方法もおすすめです。
忙しくて運動時間を確保できない人や、スポーツが苦手でなかなか始められない人は、以下の方法も試してみてください。
<日常生活でおすすめの運動>
- 徒歩や自転車で通勤する
- エレベーターを使わずに階段を使う
- ストレッチや筋トレをしながらテレビを見る
- 立ちながら仕事や読書を行う
これまで運動が習慣化せずに悩んでいた人は、日常生活のなかにちょっとした運動を取り入れる方法を実践してみてください。
健康習慣を持続するためには

運動は1日だけやっても効果が薄いため、継続と習慣化が大切です。
モチベーションを保つ工夫をいくつかご紹介します。
| モチベーションを保つ工夫 | 具体的な内容 |
| 目標を設定する | 「体重を○㎏減少」「1週間に3回走る」などの具体的な目標。 |
| 仲間と一緒に取り組む | 家族・友達・同僚と一緒に運動にトライ。 |
| 運動の記録をとる | フィットネスアプリなどを活用し、運動習慣を可視化。 |
| 小さなご褒美を設定する | 「週に1度お菓子を食べる」などのやる気が出るご褒美の用意。 |
| 運動に適した環境をつくる | 運動場・ジム、などの思わず運動したくなる場所を選ぶ。 |
| 運動習慣を宣言する | SNSで運動習慣を報告して「やろう!」という気持ちにする。 |
特におすすめの方法は「周囲の人を巻き込んで運動習慣を作ること」です。実際にダイエットの成功率を高める研究では「仲間と共に取り組む方がダイエットの成功率が高い」という成果も出ています。
友達や家族と一緒に取り組むことで、周囲と共に健康的な暮らしを目指しましょう。
専門家のサポートを活用する
自分1人では運動習慣が作れない人は、私たちが提供する「アドバンテッジカウンセリング」をぜひご活用ください。
私たちのカウンセリングでは「認知行動療法」によって、その人の「行動の変化」をもたらすことを重視しています。専門資格(公認心理師/臨床心理士/精神保健福祉士/産業カウンセラー)と豊富な経験のあるカウンセラーが対応するので、安心してご利用ください。
近年はカウンセリングやコーチングなど、専門家を活用して自らのウェルビーイングを実現する人が増えてきました。「アドバンテッジカウンセリング」は24時間・土日祝対応だからこそ、忙しい人でも気軽にご利用いただけます。
メールやWEB面談、SNSを使ったチャット相談など、幅広い相談方法をご用意しております。ライフスタイルに合わせた方法でご相談ください。
カウンセリングのご予約はこちら:https://user.counseling-platform.com/login?vid=1
サービス詳細の確認はこちら:メンタル不調者ゼロ + 社員のパフォーマンス向上を目指すなら | アドバンテッジ タフネス カウンセリング
まとめ:身体の健康増進のために運動習慣や健康管理を心がけてみてください

フィジカル面でのウェルビーイングを実現するためには、バランスのよい食事・充分な睡眠・運動習慣が重要です。まずは自身の健康状態をチェックし、食事・睡眠・運動の改善や工夫ができそうな部分を見つけてみましょう。
特に運動習慣は、いきなり運動量の多いタイプではなく、ウォーキングや自宅でできる筋トレなど、取り組みやすいことから始めるのが重要です。また、よい習慣作りには、モチベーションを上げるための工夫・専門家の力を活用する方法もおすすめです。
ライフスタイルに合わせた食事・睡眠・運動のスタイルを見つけ、心身共に健康な状態を目指しましょう!